相鉄いずみ野線延伸
概要
相鉄いずみ野線は計画当初より終着駅が平塚駅とされており、湘南台までは1999年に開業した。しかしそこから先の着工の目途はたっていない。
その後、JR相模線の倉見駅に東海道新幹線の駅を設置した上で、相模川対岸の大神地区と共に開発する「ツインシティ」計画が浮上し、いずみ野線を倉見駅まで延伸させる案が浮上した。現在では平塚までの計画は棚上げされ倉見までの延伸が検討されている。
2007年に倉見までの延伸を想定したとりまとめが公表された。とりまとめでは普通鉄道の他にLRT案、慶應大学まで普通鉄道でそこからLRTとする案も出ており、環境負荷低減と利便性向上と純益比では鉄道が勝るが、費用便益費ではLRTが勝り、事業採算性はLRT案でしか確保されないことが明らかになった。これを受けて2012年に慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスまでを第1期、倉見までを第2期として段階的に開業させるよう計画を変更した新たなとりまとめが公表され、普通鉄道による事業採算性確保の目途がついた。
上下分離方式で建設され、「都市鉄道利便増進事業」の適用により国・地方自治体・相鉄の3社で3分の1ずつ建設費を持ち合う。なおJR東海は東海道新幹線の新駅について、現時点では困難だが、中央新幹線の開業後に検討できるとしている。平塚までの計画は動きがないものの現存しており、路線が途中駅で分岐するのか倉見経由で平塚に向かうのかは未定である。
現在は2030年を目標に設定している。
路線図
歴史
1968年: 相模鉄道が二俣川〜平塚間の敷設免許を取得
1972年:国鉄が東海道開発線(新宿〜目黒〜武蔵小杉〜港北ニュータウン〜茅ヶ崎間)計画を打ちだす
※終着駅を大船駅や平塚駅とする情報もあり。
1976年: 相鉄がいずみ野線(二俣川〜いずみ野間)を開業させる
1985年: 運輸政策審議会7号答申にていずみ野線の国鉄相模線方面の延伸が答申される
1990年: 相鉄がいずみ野線(いずみ野〜いずみ中央間)を開業させる
1990年: 藤沢市が慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスを誘致
1999年: 相鉄からいずみ野線(いずみ中央〜湘南台間)を開業させる
2000年: 運輸政策審議会答申第18号にていずみ野線の湘南台~相模線方面が答申される。
2004年: いずみ野線延伸研究会が湘南台〜倉見間延伸計画を検討
2007年: いずみ野線延伸研究会が「いずみ野線の延伸に関するとりまとめ」で具体案を発表
2010年: いずみ野線延伸の実現に向けた検討会が慶応大学までの第一期整備を目指して調査を開始
2012年: 検討会が「いずみ野線延伸の実現に向けた検討会 とりまとめ」で全区間普通鉄道の案を採用し事業採算性確保の見込みが立ったと発表
2016年: 都市交通審議会198号にていずみ野線の湘南台〜倉見間が答申される
2017年: 藤沢市が駅予定地を公表
2023年:神奈川県鉄道輸送力増強促進会議が鉄道会社に東海道新幹線新駅設置、相模線複線化、いずみ野線延伸を要望
ルート案
現行案では湘南台から慶應大学までが第一期整備区間、そこから倉見までは第二期整備区間とされている。
2007年時点の全区間鉄道案では湘南台駅、新駅1、ツインシティ駅が地下駅、慶應大学駅、新駅2が高架駅となっており、新駅1〜慶應大学間で地下から高架に上がる。全区間LRT案では全駅地上駅で全線地上にして表定速度15km/hとする案と、駅間のみを高架にして表定速度25km/hとする案がある。LRT+鉄道案では鉄道区間が地下、LRT区間が地上で、乗換駅の慶應大学駅のみどちらも高架である。
2012年の普通鉄道案では全線単線で建設し、A駅が地下でB駅(慶応大学)が高架駅となる。さらにB駅の先には車両基地も設けられる。
運行計画
全区間鉄道案では2007年時点で以下の案が検討されていた。
- 10両編成、相鉄に直通
- 4両編成、湘南台で分割併合
- 2両編成、湘南台で乗り換え
- 慶應大学まで10両編成、乗り換えて倉見まで4両編成
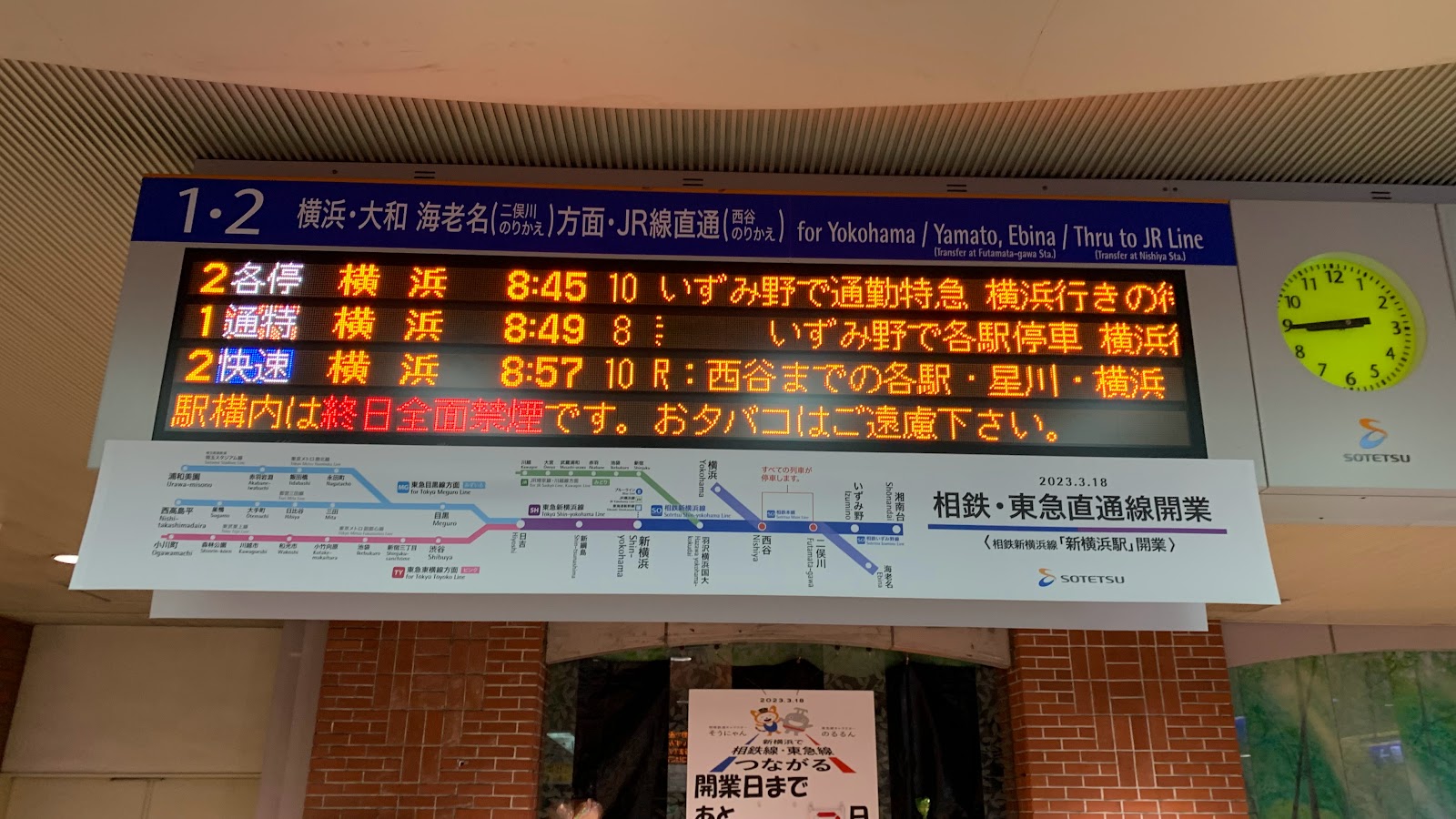



コメント
コメントを投稿